| Last updated 2017-03-24
4月20日。査読が舞い込んだ。何とか、読んで返答案を作成。少しでも暇ができると、びっくりする状況になってしまった。何故か、今日の午後は、まったりしている(仕事は一杯もっていますが)。
教育研究も忙しいが、地域的なものも、今年度バトンタッチされた事があり、大変な年度となりそうである。地域の活動を見ると、日本人の歴史を感じるが、それはそれで良い面が有る、とご助言も頂き、まさしくその通りである。
学生の研究指導は今のところ順調ではない。すれ違いというか、上手くかみ合っていない感じ。言ったことを忘れてしまう私も悪いのだが、ふと思い出して、あれ、何故XXについて全く実験していないんだろう、とか思ったりする。
研究して学会発表を聞いていると、講演会で、若手の研究者がすばらしい研究成果を(自分がやったことのように)紹介していたりする。でも、その論文をよく見ると(タイトルなど情報を見るだけだけど)、筆者には入っているけど、、、筆頭でもないし、当該のヒトがあまり柱として頑張った研究ではないような感を覚えることがたまにある。やっぱり、自分がやったと自信を持って言えるパートをしっかり持ち、自分があまり関与していない研究については、あまり自信満々に自慢すべきではないし、そうあるべきと自戒しておく。
知り合いが科研費落ちたとの情報あり。お互いホッとする? 一方で、周囲では科研費通ったヒトもちらほら。悲喜こもごも、ってのはこういうことか。前にも言ったが、現状でも何とかなるはず。成果を出し続けることが重要か。さあ、研究頑張ろう。
4月11日。サーバ切り替えの話しがありましたが、意外と私自身に関係のある事柄となりました。かなりの作業量で、パンク寸前といった状況です。未だに外部にこのページを出せていませんが、それは優先順位から言って低いし、物理的に不可能な状況です。
教務関係の仕事も多くなり、研究どころではなくなってきました(実際、自分自身のほとんどの実験研究止めています)。歯がゆいというか、腹が立つ状況ですが、まあ大人ですので、やることはやる、ということで。研究と言えば、科研費が落選しました。2件とも。毎年、腹が立つ落選通知ですが、この屈辱も糧に、研究を邁進したいと思っています。(といいつつ、研究できないこの現状・・・)
まあ、それはさておき、沢山の研究費なくても優れた研究はできますし、先見の明のある(?)ところからも研究費を補助していただいています。不満を言う前に、すばらしい成果を出さねば。それこそが研究者。貧しくても研究はできる。(言っていると寂しくなるが・・・)
しかし政府の緊急の予算?で大量のお金を使うというのに、我が研究に研究費を充てないとは、短絡的な思考だけれど、納得できんな。
研究頑張ろう。。。。
 管理栄養士養成のための新棟 管理栄養士養成のための新棟
4月3日。サーバ切り替えはなされましたが、予定と違い、アドレスの変更はありません。ですが、急な変更のため、アカウントなどが未整備の状態で、まだアップできません。現在、アップされているのは、1ヶ月くらいまえのバックアップファイルだそうで、全く関係ない先生も居られるでしょうが、更新している私にとっては、大きな痛手?となりました。とりあえず、日記がわりに現状をご報告します。
その他、食環境栄養課程がこの4月から立ち上がり、新任の先生方も来られている。色々わからないこともありましょうが、できる限りサポートしていきたい。といいつつ、諸々作業が多すぎて、こなしきれない状態に。仕方がないから、実験を少し止めるしかないという悲しい現実・・・。
3月25日。
4月からサーバ切り替えのため、URLが変わります。詳細は未定です。いつ復旧・再開できるかわかりませんが、4月以降に、新サーバから我が研究室のサイトを探して下さい。その他、学部ホームページも、食環境栄養課程のページも、しばしリンク切れなどかなりの支障が出るかもしれません。ご容赦ください。
3月20日。祝日だけれど、公務で朝に会議。
昨日は、学生と一緒に不調になったiMac 17インチ、G5マシンのメモリとHDを新品に換装。それぞれ倍程度の容量となる。OS入れ替えは月曜日を予定。OSが未インストールながらも、起動することは確認。不調の原因はHDであろうと思っている。トルクスドライバーなる特殊工具も、学生に買ってきてもらった(お金は出してます)。
以前、細胞の実験を、という話しをしていたと思うが、細胞を6万円(税別)で購入し、少しずつ進め始めた。最初は増やしてストックしなければならないため、実験どころではないのだが(最初にコンタミしたらアウトなので特に気を遣う)、ようやく少し細胞量に余裕が出てきた。そこで、急ぎ実験。その時の絵を少しだけ紹介。色々条件検討しなければならないのだが、緻密な実験は、性格的に向いていないなあ、と改めて思う。小さなパーツをくみ上げるよりは、大きなパーツをざっくり、ひょいっと載せる、というスタイルが自分に合っている。
大まかな道を作り(探し)、あとは、学生に綺麗に舗装してもらう、という流れが我が研究スタイルにとっては、ベストなのかなと思うけれど、現実はなかなか上手く流れないものである。
もうすぐ春、そして講義開始。委員会やらの仕事も増える。すなわち実験をやる時間が減る。(実は次年度以降なのに何故かすでに委員として年度末にも仕事を幾つもやってもいるのだが) 今がデータのかき入れ時なのだが、なかなか、上手く時間がとれないものである。色々仕事を引き受けたり、自ら買って出たり、と自らを反省する必要はあるが、まあ、研究よりも人間マター、を最優先するべき、という信念も持っているため、(言い方は悪いが)「平均以上」の人助けはやるべし、と思っている。
 染まる細胞 染まる細胞
3月17日。追記。iMac(24インチ)の方は、我慢できずに注文してしまいました。学生へは、お古を手渡す予定です。ひたすら実験して疲れました。
3月17日。世の中、腹の立つこともあるが、罪を憎んで人を憎まず。がまん。
学生のiMacが不調になったとのことで、どうやらHDのトラブルかという感じ。これは、困った。ということで、急ぎ内蔵HDとメモリをwebで注文した(支払いも済ませた)。到着はいつになる事やら。また、一緒にOSもアップするつもりで、それは生協に注文した。一体型iMacなので、上手く換装できるか不安な面もあるが、とにかくやってみるべし。当該iMacは、比較的、換装が容易なタイプらしい。
我がMac miniをiMacに、という計画はすでにご紹介したと思うが、ようやく、「ご注文頂ければ数日内に納品可能」、との連絡有り。しかし、基本的に時すでに遅し、で、他の物品を買うべく諸々の処理中。という状況で、別枠予算か、プライベートマネーのいずれかで買うか、(あるいは買わないか)という判断を迫られる。上述したようなトラブルもあり、ニューカマーの話しも有り、今が買い時なのではある。
実は、Group meetingに使える机も見積もりを取ったのだが、納期1ヶ月以上、ということで、年度内は、あえなく断念。こういうデスク製品って、受注生産が多いのね。
 ノウバケ学会2009 ノウバケ学会2009
3月12日。学会迫るが、ポスターなので緊張感薄い。
元指導学生の論文の要旨(アブストラクト)がWebで読めるように。リンク先は こちら。ファーストでもラストでもないが、コレスポンディングになっています。Article in press、を見ていたら、色々興味深い論文がずらり。いやはや、世界は進んでいる。我々の論文はどれほどのインパクトがあるのか、後世(後生)にどれほどの影響力があるのか、を問い続けなければならない。 こちら。ファーストでもラストでもないが、コレスポンディングになっています。Article in press、を見ていたら、色々興味深い論文がずらり。いやはや、世界は進んでいる。我々の論文はどれほどのインパクトがあるのか、後世(後生)にどれほどの影響力があるのか、を問い続けなければならない。
研究室のレイアウトを少し変更しました。少しは使い勝手もよくなったかも。
日本語の書籍の一部執筆のゲラが来た。急いで作ったので、幾つもアラが見つかる。冷や汗である。簡単な所は直せるが、大きくは修正できないので、どこかで折り合いをつけるしかない。
英語の査読の返却を昨日した。論文を書くのとまた違って、相手が見える作業なので、気を遣う。日本語でも相手を意識すると文章は書きにくいが、英語ならなおさら丁寧に表現したりということがスキルとして無いので、いつも困る。こんなことでは自分自身困るのだが、英語の勉強よりも、実際の実験やその他のことを優先したツケがまわっていると言えて、自業自得ではある。
メールの転送というのを行っているのだが、よく言われるようにG-mailなどの迷惑メールフィルターは優れていることを実感する。細かな事は省くけれど、転送、転送、転送して携帯端末からメールを読めるのだが、迷惑メールはほとんど届かなくなった。心理的によろしいいことだし、パケット代の節約にもなる。
 Free Radical Biology and Medicine(通称 イエロージャーナル) Free Radical Biology and Medicine(通称 イエロージャーナル)
3月8日。日曜日です。培養細胞のケアのために来ました。ついでに、HPLCの環境を少しいじる。オートサンプラーが1台あまり使われずにういている感じなのだが、もったいないので、旧型HPLC--オートサンプラー--旧型-UV検出器---蛍光検出器(枝分かれしてインテグレーター)---廃液という流れを作ることにした。新型HPLCはUV, 蛍光ともに使えるのだが、オートサンプラーが無く、かつ、既存のオートサンプラーは組み込めない。なので、旧型にオートサンプラーを組み込むしかないのだが、蛍光検出器が使いたい。そういうのを解決するべく、作業して、少し試運転してみたら、何とか運用できそう。まあ、基本的にこれは、良い(安定した)成果が出ていない学生の負担を少しでも減らすための工夫なのではあるけれど。
iMac、購入を考えているが、納期が今年度中に間に合うか微妙らしい。きっちり年度内納品、というのは、案外重要なファクターであり、公、としての職業に就いていると、なかなか毎年大変なことなのです。あとは、ミーティング用テーブルの購入も考えていますが、部屋が狭いので、小さな机しか買えず、イメージしていたエレガントなミーティングは無理っぽい。
明日は、少し気を引き締めて取り組むべき要件もあり、昨日は散髪を決行。そうそう、金曜日に歯のぐらついていた詰め物が取れて、ある意味、すっきりと歯医者に行けた。ではまた。
3月6日。細胞は新しく注文することにした。凝集しやすいらしいので、大変かもしれないが。その他、アップルからiMac, Macminin, MacProなどが新しくなって販売されている。Macminiを購入、と考えていたが、現状のマシンとさほど性能は変わらないし、メモリを4GBにアップさせ、CPUを一段階あげ、などしていたら、10万円を超えて、iMac24インチの15万円程度と変わらなくなってしまう。外部モニターはあまり気味なので、モニターの付属していないMacminiでも充分なのだが、、iMac24インチにすべきかという状況である。急ぐ必要は無い、と言いたいところだけれど、学生が1名あらたに加わることがわかったため、Macを追加で1台欲しいところ(あとは年度末、のおきまり駆け込み需要?)。おさがり、というと感じが悪いかもしれないけれど、私の現行(現役)のマシンを学生に譲るか、という考え。お下がりでも、実は、学生用の既存2台のマシンよりも高性能です。
学生の実験が上手く行っていないため、どのように助力するか、考えている。私の場合、基本を伝えて、細かな所はお任せ(=見張る、ということはしない)、というスタイルなのだが、データにバラツキがあったり、出るべきピークが微少ピークであったりすると、どこに問題があるか、突き止める必要が出てくる。まあ、やってしまった方が早い、という話しも有り、それを学生に追試してもらう、という手もあり、悩みどころである。
あとは、研究室に人員が多くないため、また、歴史も浅いため(伝統がない、と言えるか)、技術や情報の学生間での伝達が不十分である。それを補うために、私が直接教えることも多いのだが、それはそれで、学生同士での問題解決あるいは助け合いのチャンスを奪っているとも言えるわけで、そのあたりの案配が難しい。まあ、そんなことは学生は気にしてもいないのだろうけれど。
NZでは週に1度、Group meetingがあった。研究室が大所帯なので、2分割して研究報告をしていた。といっても、誰が担当とかなくて、データがある人が実験ノートを片手に報告する(プレゼン資料無し)。テーブルの反対側だと、掲げているノートの字は全く読めないのであるけれど。大学院生も活発にコメントしたりして、研究に対する考え方、議論、などなどのトレーニングの場になっているのかなと思った。日本以上に、そういう場での立ち姿を教員は見て、学生をきちんと評価している気がする(研究者に向いているかどうかを判断してレベルアップをどうするか判断していく感じ)。証拠はなくて、そう感じただけだけどね。空気を読んでの感想です。英語が苦手で、帰国直前までいい成果がでなかった私には、苦痛な気がしたけれど、サボることはなかった。2回くらい(たったの)最新のデータを紹介したかな。なお、このmeetingでは成果を報告するだけではなくて、上手く行っていない場合も皆の知恵を出し合う、という感じで紹介する。これも、なかなか実現しにくいことだよなあと思っています(日本人の研究スタイル的には)。
ニューカマーも来ることだし、学生同士の情報交換も促進するため、次年度からGroup meetingを週1で開催することを提案したい(総勢4名なので場所は我が居室を想定)。毎週、すくなくとも「私」が紹介できるように、実験する時間を捻出したいと思っている。学生からの紹介(良いも悪いも)は、あまりないかもしれないけれど、それはそれで、「評価」の対象に加えたい。
少数精鋭、そんなキーワードで攻めたい我が研究室である。(人数はあまり必要ない、というか、現状では、私が多人数に対応しきれない・・・)

3月2日。諸々に終われて、実験する暇がない。培養細胞を再びやるか、という段階だが、既存の株を使うか、あらたな株を購入して使うか、悩んでいる。
加えて、その培養細胞の実験研究を成功させるため、少し周辺情報を集め始めた。といっても、雑誌のアブストラクトを読むだけではあるが。世界は広い。色々な研究がなされている事に驚かされる。将来、誰かも私の関係した研究論文を読んでくれるかもしれないので、それはモチベーションになる。卒論発表会やら、他の研究分野の発表で、気になる点は、やりっ放しの研究で終わってしまっていないかという点である。自己満足で終わる研究、自己完結してしまうものは、私にとって見れば、意味がない。自分が途中で倒れても、そのあとを誰かがついで更に発展が続いていくというイメージなのだ。調べた、でもそれでおしまい、では寂しい。サイエンスの楽しいところは、やっぱり、ヒトのやっていないことをやることだけれど、プラス、それが今の、あるいは将来の誰かの役に立つ、基盤になる、という点かな。
MacのiWorks 09を使い始めたが、エラーバーが出せるようになったというグラフソフトを期待したけれど、駄目でした。誤差の指定ができない。そこを治してくれたら、まあ使えると思うのだけれど・・・。やはり、Excelだのみは変わらない。一方で、Excelも2008(Mac)になってから、コピーした図が絵として貼り付けられるようになってしまい、加工できない状況となった。改悪といってもいい。単独では見栄えの良い絵になっているのだが、論文に使ったりするには、、、。カレイダグラフも使っているので、回避できる場合もあるのだけれど、カレイダも苦手なグラフがあったりする。

2月27日。英語の論文について、少しお手伝いしているものがあるが、一応、ラフではあるが、作業を一先ず終えて、他人にバトンタッチ。論理を紡ぐ作業は、しんどいけど、ある意味、楽しい。でも大変。この1つの文章、さらに続く文章、そして全体へ、などのつながりを感じながら書いていく、ってのが、ひとつのスキルなのかなと思ったりします。そんな過程で、学生時代には見えなかった森や山も見えてくるけど、学生時代に見えていた林の一部は見えなくなっているように感じます。
一方、大学での事務的な事柄、会議などでも、論理は大切です。単に感情的な意見はとても困ります。ただ、最近思うのが、大学人は、論理、ロジックにとらわれすぎていることが多いのではないかなと言うこと。研究そのものは、ロジックですが、大学運営や教育、人間ってのは、理詰めではないと思うからです。多面的にものを見ることが大切で、そのためには糸を紡ぐようなロジックはかえって邪魔になることがあるのでは、と思います。まあ、そのあたりは皆わかっているのでしょうが、線を引くのが難しいですね。グレーゾーン(曖昧さの許容範囲)をどれほど確保しているかは、個々人によりましょうし。
あと、最近思うのは、大学人は、公共性をやはり持たなければならないのでは、ということです。産学連携などがもてはやされ、外部資金、外部資金と言われますが、それはそれで良いのですが、地域を、日本を、さらには世界を持ち上げるような美しい「志」がもう少し必要なのでは、と思わされるケースがたまに、ですが、見受けられます。研究者はお山の大将なので、自分の領土を上手く統治していれば、あるいは、自分の領土が富めば良いのかもしれませんが、人間、やはりそれではいけないと思いますし、特に大学に暮らす人間としては、もっと広い、高い視野から、周囲を見て、色々配慮していく必要があるのだと思います。それこそ、ロジックではない部分、愛郷心、愛国心、地球愛、につながるのではと思います。

2月22日。日曜日です。一つ、査読を返却。肩の荷が下りた、と言いたいところだが、少し前からリクエストの来ていた別の査読を受け入れることに・・。内容的に、パスできる知人を思い当たらなかった。まあ、私に振ってきたヒトも、適任者を思いつかずにパスしたのかなとも思ったりもするけれど。じゃなければ、これほど分野外のネタを査読させようとは思わないだろう! 誰か知らないけれど、うらみます・・・・。論文を読む機会の減った私にとっては、ある意味、強制的な文献購読なので、プラス面はあると思います。(とでも思うしかない・・) とにかく、英語で言いたいことを言うことが大変なのだ。
あと、iPodtouch(2G)を購入し、カレンダー、メモやメールチェックに使おうと思い立った。実行移したまでは良かったが、大学内ではWiFiで同期できず(これはある程度覚悟していました)、別に購入したMissing syncによるメモの同期もできない。メモの同期ができるって、書いてあった、と思って、当該会社のディスカッションフォーラムみたら、できないらしい。バージョン2まで待ちなさい、ということのようだ。詐欺じゃないかとも思ったりもするけれど、まあ、しばし、我慢してまとう。
あと、WiFi でしかつなげない(iPhoneみたいに3Gでつながらない)podtouchでどのようにメールやウエッブ閲覧を実現しようかと思案中である。今のところ、データ通信カードプラス端末、みたいなものが候補か。これまた携帯みたいな契約が必要で、諸々考えると、iPhoneでいいじゃん、ってなりそうな気がする。でも、個人的には携帯そのものは、通話にはあまり使わないので、、、。
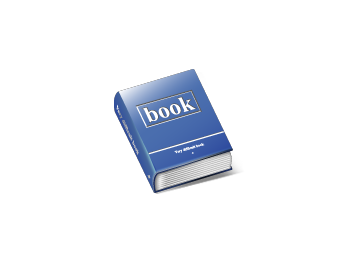
2月19日。卒論発表会がありました。皆さん、頑張って居られましたね。上手なプレゼン資料ですが、原稿を読んで発表している人が多かった点は、残念に思います。数十分しゃべるならまだしも、10分程度の原稿なら、丸暗記してこい、と言いたい。前を見るように努力しているようだけれど、、、ねえ。まあ、たどたどしく暗記を思い出しながら話すよりは良いのかもしれないけれど。名演説、をする人って、原稿を読みながら話すのかしら、と思ったりします。
といいつつ、年なので、記憶力が衰え、アドリブで話すことが多い自分を少し反省しなければ。。。
学生の論文がようやくwebで読めるように。といっても、我が学部は契約していないので、PDFが有償となる。。。ご興味のございます方は、 こちらから。あまり気にしていないが、2007のIF(インパクトファクター)は3.5とか。数値以上に、存在感が上がってきている雑誌と思う。 こちらから。あまり気にしていないが、2007のIF(インパクトファクター)は3.5とか。数値以上に、存在感が上がってきている雑誌と思う。
また、かつて在籍した学生の論文がアクセプト(論文にしますと判断)されたとの連絡あり。web上でほとんどが処理されるため、修正版をアップロードしたけれど、それを1本化したPDFファイルのダウンロードに苦労していたのだが(それを見てから修正版としてeditorに送る手順)、原因不明のまま、結局、編集部(と出版社)からPDFファイルをメール添付で直送してもらい、それをもとに修正版として確認ボタンを押し、翌日にはアクセプトとなった。こちらのIFは4.8とか。こちらについては、また後日、詳細をご報告します。
その他、ドタバタしています。そんな話しはまたの機会に。
 Chem. Res. Toxicol. Chem. Res. Toxicol.
2月12日。結構、多忙です。共同執筆の原稿(日本語)を急ぎ仕上げました。少し分野外の、というか、直接関与していなかった所まで作文したため、大変だった感じがします。あと、英語の投稿論文用の追試を終え、回答案を作り、スペルチェックに出し、早速返却されています。実は、ドルが安いので、いつもの海外に依頼を、と思っていたら、日本のサイト(代理店のようなところ)に契約を解除された、とあり、信頼性の問題があるので、取りやめに・・。で、何度か使って安心な別の業者に依頼。回答レター案なので、文字数が少なく、料金も控えめ・・。ちなみに、それでもたっぷり英語を直されています。あとは、共同研究者の執筆論文について、少しコメントをしたりして、こちらは相手がしっかり対応されているので、私の方はとりたてて時間を割かれることもない。いよいよこちらは投稿でしょう。楽しみ。あとは、引き受けてしまった査読について、そろそろ見なければ、というところだが、、、、。月末にある研究会の学部紹介プレゼンもぼちぼち、作成を進めています。
大学の事務的な仕事は、まあ、いつも通り、それなりに。会議が多くてげんなりする。私自身の研究は、上記したような雑用で2,3日ストップしている感じがあります。残念。明日からは、現場復帰したいと思っています。
あと、乾熱器という装置が壊れました。温度が上がらなくなってしまいました。修理を問い合わせたら、8年前に作られた装置で補修用のパーツも無いので修理対応できないとの回答。まあ、ありがちだけど、日本って、これでいいのかなあと思ったりもする。無理に修理もできるだろうけれど、人件費や技術料の方がかかるかもしれないし、そういう職が無くなっているのだろう。ニュージーランドだったら、間違いなく人が来て、2,3時間で治して帰って行っただろうなあとおもいつつ、結局は、新しく注文することになってしまった。なにせ、乾熱滅菌という処理に使うため、培養細胞の実験に支障があるので、壊れたままにしておけない。(といいつつ、学生の様子からすると、培養細胞で良いデータは出ていないようだけれど)
故障と言えば、カラーレーザープリンターの色ずれがひどいのだけれど、さすがに限界で、カラーインクジェットプリンターでしばらくしのぐことに。年度末のため、予算もあまり無い状況で、2万円弱で複合機を購入。今回はその雄姿をお見せしましょう。ちなみに、このメーカーのプリンターで、一度、痛い目にあっているのだけれど、さて、今回はどうかな。(保障期間が過ぎた頃に壊れるってのはやめて欲しいなあ・・・) 安さで購入だけれど、これまた壊れたら廃棄ってことになるのかなと。壊れつつあるカラーレーザーは修理費と新品購入費がほとんど一緒なので、修理をあきらめています。(もっとも、購入した時の値段は、もっと高いのだけれど、技術革新で結果的に同等性能の機種がかなり値下がり・・)
 新入りプリンター 新入りプリンター
2月2日。某元指導生のための追試実験を継続中。まあ、4勝6敗って感じかな。それなりに新しい条件もわかったりして、有意義な点はある。FRF2研究室の学生さま2名も、皆頑張っているし、4月から新戦力が加わる可能性も高い。これで研究費があたれば、言うこと無し・・。
現指導学生の最初の論文のゲラ刷りが来ている。オンラインでほとんど済ませられるあたり、世の中、便利になったものである。しかし、こうしていわゆる雑誌、みたいにフォーマットに収まった我々の論文をみると、それなりにいけてる、という感触を得る。あ、しまった、別件だけれど、査読依頼について、回答していない・・・。どうしよう。大変だけれど、引き受けるか・・・。(引き受けない場合は誰かにパスしなければならない訳だし・・) 今から返事します・・・。
写真は、ぶつかり防止の工夫。我が学部、内開きだったり、外開きだったり、色々なので、逆と思って突進して、たまにドアに衝突する。(ホームセンターで買ってきました)
 今日の工夫 今日の工夫
1月26日。JCBN誌に受理された論文を掲載した雑誌が届き、また、WebでもPDFファイルが入手可能なことを確認しました。内容は、簡単に言えば、チロシン修飾物のLC/MS/MSによる網羅的検出定量です。読みたい方は こちら(PDF)から。 こちら(PDF)から。
今日から某元指導生のための追試実験を開始。一発で上手くデータがでると良いが。自分の実験する時間を削ることになるので、その点が悔しい。今日など、デスクワークばかりである。とはいえ、基礎ゼミナールの総決算である発表風景ビデオをDVDに焼いたりと、それなりに意義のある昼間ではある。
 isotyping (immunochromatography) isotyping (immunochromatography)
1月20日。研究室名を変更します。FRFF Lab.ということでお願いします。
ようやくNZ研究者と連絡が取れましたが、2週間の休暇にはいるそうです。その間にまた成果を量産しておくか、という意気込みで頑張ります。
MacworldではMacminiが発表されず、残念。今のまま、しばらく使い続けます。自宅のPowerBook G4も自宅で使い続けることにして、自宅のMacmini(これまたNZで仕事場で使っていたもの)を学生用に大学に持ってきました。
 ププスプリング(NZ) ププスプリング(NZ)
1月5日。あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
新年めでたいということで、正月、自宅用にMacBookをぽちっとな、しました。勿論(?)、キーボードはUS配列です。「キーに付いているひらがな表示」が嫌いなので・・。クロック数は低いやつ(2.0GHz)ですが、ハードディスクは少し容量をあげました。自宅のPowerBook(NZまで旅した相棒)の処遇を考えねば。研究室のMacminiについては、今度のMacworldでいいやつが発表されたら、買い換えたい(買い増したいか?)。
今年の希望として、例年通りに教育は頑張るとして、
・進行中の論文をアクセプトさせたい(x2+1)
・NZから引き続きのネタを更に発展させたい
・細胞生物学、分子生物学に少し足をつっこみたい
・ブレークしたい(研究面で)
をあげておこう。
 ほぼ2年前にNZで撮影した1枚(誤差1日) ほぼ2年前にNZで撮影した1枚(誤差1日)
12月29日。今年最後の更新にしたい。モノクロ作成が佳境に入ってきて、年末に微妙な、、。ということで、こうして研究室に来ているわけ。あと、NZ研究者にも最新のデータを郵便(EMS)で送る。で、培地暖め中なので、細胞のお世話をしたら帰宅する。本当は動物室の掃除があったのだけれど、午前中に家の窓掃除などしていたら、すっかり忘れてしまっていた。すみません。いやあ、ドタバタしていると諸々おろそかになっていかんなあと反省。
 いよいよ2009。 いよいよ2009。
12月25日。質量分析器(というよりもその一部)が壊れた。この時期に大変である。繰り越せないとか、ためられないとか、頼る埋蔵金がないとか、色々問題がある。まあ、身分不相応な機器を使っていると言えばそうなので、痛い目を見るのは致し方ないかも。研究費は少額でも、と思ってはいるものの、こういう事態になると、たっぷりあった方が良いなあ、とも思ってみたり。
研究費ネタで言えば、論文投稿を2報ほど進行中であるが、スペルチェック代でかなりの出費である。かつ、前に受理された論文(こちらはNZ留学前の研究)で、page chargeとやらが10万円近く請求された・・・。あわせると20万円近くの出費だと思うが、現在の所、立て替え払い中である。研究室の残予算にもよるが、おそらく、数パーセントまかなうかどうか、、、で、残りは・・・・。
NZ研究者からのクリスマスギフト(論文の共同作業成果)は届かず。英語の勉強で言われることだけれど、意思表示することが大切、と言われるため、やっぱりなあ、催促するかあ、という感じ。日本人との感じ方の違いを克服することは難しい。(私は、日本人としても、はっきり物事を言う方だと思うけれど)
 予算の話しはよさんかい。 予算の話しはよさんかい。
12月19日。寒くなるとNZにいた頃を思い出す。今頃は初夏の雰囲気かもしれないけれど。今後の研究方向性を悩むことが多くなってきた。良い傾向かもしれない。実験研究は木を見る、という作業がメインだが、森を見る、ということも大切。なので、方向を考えることは森を見る、山を見ることにつながるので、将来につながる。
研究をやっていて、感じるのは、高揚感、というか、使命感、というか、やってやるぜ、という感覚。他の人の存在は,基本的には関係ない(的確な評価はされたいが)。これがあるから、これまでやってこれたし、これからも(しばらくは)やっていけるだろう。
NZ研究者との約束で、研究成果をクリスマスまでにまとめよう、という話しがあったが、どうなるやら。あちらからのギフトも楽しみ(不安)だが、こちらからもサプライズとまではいかないが、吉報をギフトしたい。スケジュール的にはぎりぎりだが、間に合わなければ、日本人的に正月あけましておめでとう、ということで、研究成果の進展を報告したい。とはいえ、これからが勝負。やってやるぜの精神で、研究に邁進しなければ。
なお、これまでのTopicsは 保管庫に移動させました。 保管庫に移動させました。
 遊歩道 in NZ 遊歩道 in NZ |








 こちら
こちら







 保管庫
保管庫

















 HOME
HOME
 別館
別館 環境人間学部Web site
環境人間学部Web site 前のページへ
前のページへ 次のページへ
次のページへ