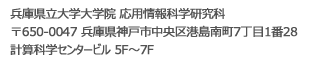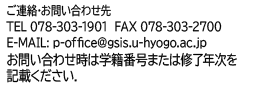|
|
 |
| 政策経営情報科学コースでは、行政や政策にかかわる情報の収集・分析・処理、政策立案、あるいは環境・経済問題などを取り扱う様々な情報システムの構築と運用にかかわる応用技術に関して、実用的な研究開発を自立して推進できる創造的な研究者や技術者、あるいはフィールドワークや産官学共同研究を通じて社会に役立つ技術開発を独力で実行できる高度専門職業人を育成しますが、この目的のために、本コースを「政策情報学」領域と「経営情報学」領域の2領域で構成しています。 |
| ・ |
ICT(情報通信技術)革新に伴う新たな企業経営戦略の可能性 |
| ・ |
流通、製造、およびサービス業における無線タグの活用手法の開発とビジネスモデルの構築 |
|
| ・ |
社会、経済、交通、医療、危機管理などグローバルな視点から統合化された環境モデリングとシミュレータの開発 |
| ・ |
温暖化に関する国際環境政策や環境課題の検討と、多目的な森林生態系と環境経営の役割の評価 |
|
| ・ |
GIS(地理情報システム)を利用した企業の立地の動向に関する計量的研究 |
| ・ |
電子自治体化が地方自治体及び地域社会に及ぼす影響についての政策論的観点からの研究 |
|
本コースは、「政策情報学」と「経営情報学」の2領域で構成されています。 |
 |
政策情報学領域 |
 |
| 政策情報学領域は、行政や政策にかかわる情報科学技術の応用に関する高度な教育研究を目的としています。近年の情報ネットワークにおける急速な高性能化と多機能化により、行政機関の電子化が急速に進められています。そのような状況下で、多元化する大量の政策情報を効率的に処理し、可能な解の中から最適解を人為的に取捨選択することのできる情報システムをいかに構築するか、電子認証の導入に伴う情報セキュリティにかかわるリスクマネジメント及びデータの検索、保存、及び暗号化をいかに行うか、について解決手法を模索し、それらを行政現場においていかに活用するか、という課題が重要となっています。本領域においては、現在明らかになっている重要テーマにとどまらず、電子政府・自治体の本格的稼働に伴って惹起される未知の問題をも視野に入れて、行政と政策に関する情報システム化に関する教育研究をも推進します。また、本学が位置する兵庫県が森林資源や自然環境の多彩な空間的広がりを有し、環境情報に関する教育研究の素材に恵まれた地域でもあるという利点を生かし、本研究科は環境問題などの学際的領域に関する情報の分析及びシミュレーションに関する実践的な教育研究にも焦点をあて、社会科学及び情報科学技術の複眼的視点から、現実の行政及び政策への高度な応用に関する独自の教育研究を推進します。 |
| 本領域修了者の活躍が期待される場 |
| (1) |
地方自治体における企画、情報システム、情報セキュリティ、環境の各部門 |
| (2) |
地域経済団体における企画、立案、起業支援、中小企業への情報化支援の各部門 |
| (3) |
地方公共団体における産業、中小企業対策支援等の各部門 |
| (4) |
民間のシンクタンク等の研究員 |
| (5) |
情報あるいは総合政策系の大学、専門学校 等 |
|
|
 |
経営情報学領域 |
 |
| 経営情報学領域は、経営における情報科学技術の応用に関する教育研究を目的としています。経営活動においては、例えば、資材調達に関するSCM(Supply Chain Management)、企業戦略に関連して経営資源の有効活用のためのERP(Enterprise Resource Planning)、営業活動に関連する電子商取引(Electronic Commerce, e-コマース)、顧客管理に関連するCRM(Customer Relationship Management)、社員教育に関しての電子学習(Electronic Learning, e-ラーニング)、企業経営全般に関してのBPR(Business Process Re-engineering)、企業経営の意思決定に関するデータ解析やデータマイニング、企業内の暗黙知を明らかにするナレッジマネジメントなどが具体的な教育研究課題となります。また、企業でのマーケティング活動において注目されているエリア・マーケティングや地方自治体で注目を集めている空間的な属性に配慮した地域のマネジメント手法とこれらの手法の基礎となる地理情報システムについての研究も行っています。更に、情報科学技術を実社会へ応用し、生活での利便性や安全性の向上を図ることによって、新たなビジネスの創出やマーケットの拡大や収益性向上が可能となります。これに関連する教育研究として、モーバイル情報通信、情報家電、あるいは電子タグにかかわる技術開発に関する工学的研究が含まれます。以上の経営活動にかかわる情報科学技術についての教育研究の課題は、企業や自治体にとどまらずNPOやNGOなどにおいても適用しうるものであり、本領域ではこれらの経営情報に関する高度で実践的な教育研究を推進します。 |
| 本領域修了者の活躍が期待される場 |
| (1) |
企業における経営企画、情報システム、情報セキュリティの各部門 |
| (2) |
地域経済団体における起業支援部門、中小企業の情報化支援部門 |
| (3) |
地方公共団体における起業、情報化支援や中小企業対策等の各部門 |
| (4) |
シンクタンク等での経営コンサルタントやSEの各部門 |
| (5) |
情報、ビジネス、商学、環境系の大学、専門学校 等 |
|
|
| 近年の医療技術の急速な進展により、多くの難病や不治とされた病に対する治療が可能となっている反面、生活習慣に起因する慢性病の患者が増大し、働きながら治療やヘルスケアが必要な患者が増加しています。また、高齢社会の到来により、在宅での継続的な治療やヘルスケアが必要な長期療養者も増加し、地域医療への新たなニーズの高まりと課題の提起がなされつつあります。このような状況を踏まえ、従来の病院を中心とした医療体制から、地域社会に根ざした疾病予防と健康維持を重視した広域的なケア体制への転換が社会的に要請されており、その実現には、病院や地域で行われている診療や健診だけではなく、ヘルスケアに関する情報の統合化と共有、及び情報システム化が重要な鍵を握っています。ヘルスケア情報科学コースでは、今日ますます複雑化しかつ多様化しているヘルスケア情報を分析・統合化し、施設や地域における保健・医療・福祉の効率的な運用を図るために必要な情報システムの構築と運用にかかわる研究開発を独力で推進できる創造的な研究者あるいは高度専門職業人を育成します。そのために、「医療福祉情報学」領域と「看護情報学」領域の2領域で構成しています。 |
| ・ |
マルチメディアを用いた生体情報解析による在宅医療のための遠隔医療システムの開発 |
| ・ |
遠隔看護における体温・脈拍・血圧等のバイタルサインや指尖容積脈波などの新たな看護観察情報の有効性の検討 |
| ・ |
周産期医療における健康管理のためのモニタリングロボットの開発 |
|
| ・ |
柔軟な知能化技術やニューロインフォマティクスの知見に基づいた情報アプローチによるヘルスケア諸課題の解決 |
| ・ |
脳波や心電図などの生体時系列データの解析とパターン認識による疾病の早期発見および早期治療に関する研究 |
| ・ |
生体画像情報からの異常パターンの検出による病態把握と適切な治療選択のための応用 |
|
| ・ |
医療・福祉の安全をはかるためのIC(無線)タグの応用 |
| ・ |
最先端医療機器を用いた医療検査結果解析および患者に分かりやすいバーチャル3次元可視化診断システム |
| ・ |
電子カルテ構築における看護行為の標準化とメタデータベースの妥当性と検討 |
|
| 本コースは、「医療福祉情報学」と「看護情報学」の2領域で構成されています。 |
 |
医療福祉情報学領域 |
 |
| 医療福祉情報学領域は、検査、診断、治療、薬剤、看護などの診療に直接かかわる情報だけではなく、医事・病院管理に関する事項や疾病予防、健康管理、あるいは介護に関する多様な医療福祉情報の分析や管理を行うための処理方法、あるいは情報システムの構築や運用に関する教育研究を担当します。具体的には、電子カルテ、遠隔医療システム、医用画像処理、あるいは医用データマイニングなど、医療情報システムのサブシステム、コンポーネント、あるいは技術要素にかかわる情報処理技術の研究開発、更には生体・脳・ゲノムなどの各種生体情報の解析と応用に関する高度な研究開発を推進します。また、この領域は、人々への医療情報や健康情報のほか、インフォームドコンセント、健康意識と予防、医療保険制度、医療経済、高齢社会と介護保険制度などのような医療と行政が密接に関連する情報に関して、科学的根拠に基づくヘルスケア(Evidence-Based Healthcare, EBH)と情報セキュリティの観点から、エンドユーザである人々が必要とする医療福祉情報を効果的に提供可能な情報システムの構築について実践的な教育研究を行います。 |
| 本領域修了者の活躍が期待される場 |
| (1) |
病院の医療情報部、病歴管理部、画像診断部門、リスクマネジメント部門 |
| (2) |
医療情報系大学・医工学関連大学 |
| (3) |
医工学関連研究施設 |
| (4) |
各地方自治体医療・保健・福祉サービス関連部門 |
| (5) |
医療・福祉情報システム構築企業 |
| (6) |
医療・福祉機器、ロボット製造企業 等 |
|
|
 看護情報学領域 看護情報学領域 |
|
 |
| 看護情報学領域は、病院や地域における看護・介護情報のデータベース化と、その効率的な運用を基盤として、情報システム化により看護・介護サービスの内容の向上と効果的・効率的なサービスの実現を可能とするような研究開発を行っています。看護分野において情報システムを構築する際には、各種データベースの標準化と情報システムの実装及び評価が重要な鍵ともなっています。また、医療環境の変化に伴う在院日数の短縮により、看護実践は高度化かつ複雑化しているため、情報科学技術を活用して、看護介入のアルゴリズム化や看護実践の可視化に向けてのシステム開発及び評価を行うことのできる人材の育成が要請されています。さらに、在宅療養者の増加によって、看護・介護支援のための情報ネットワークの構築も求められています。このような在宅看護・介護支援のためのネットワークを基幹にした地域の在宅ケア支援システムの研究開発や効果的な運用に関する実践的な技術開発が推進できる人材を育成するのもこの領域です。 |
| 本領域修了者の活躍が期待される場 |
| (1) |
病院の看護部(とくに看護管理部門)、医療情報部、リスクマネジメント部門 |
| (2) |
訪問看護ステーション、在宅看護支援センター |
| (3) |
看護大学・看護学校 |
| (4) |
各地方自治体医療・保健・福祉・介護サービス関連部門 |
| (5) |
医療・福祉情報システム構築企業 等 |
|
|
| 1990年代には、情報の安全・安心は、暗号技術に代表される技術的視点からのみ論じられてきました。その後、阪神・淡路大震災等の災害からの教訓、個人情報保護基本法等の情報セキュリティの法制化、大規模な粉飾事件の頻発などの影響により、“情報の管理”の重要性にも焦点が当たるようになりました。その一方で、インターネットを利用したサイバー犯罪が社会の耳目を集め、情報を利用する側のリテラシーの重要性や、人との親和性の面から情報とその環境の“質”そのものに関する課題も提起されています。これらの観点はどれも等しく重要であり、統一的な枠組みの中でバランスよく論じられるべきなのですが、なかなかそうはなっていません。本コースでは、人々が“信頼をもって情報を活用でき”、しかも持続的に受容される高信頼なシステム・環境の実現を目指して、学際的なアプローチを駆使しつつ、情報の安全・安心と質にかかわるテーマに多面的に取り組みます。その中で、情報の安全・安心と質に本質的に備わる多様性を理解し、高信頼情報科学技術の専門家として社会のニーズに応えられる人材の育成を目指します。 |
| ・ |
情報インフラの安全・安心を支える、暗号・プロトコル設計・アクセス制御・検知技術などの情報セキュリティ技術の研究 |
| ・ |
安全・安心な情報システムを実現する、ポリシー・リスクマネジメント・事業継続計画などの情報マネジメント手法やディペンダブルソフトウェアなどのソフトウェア技術の開発 |
| ・ |
情報の安全・安心な利活用を促す、個人・学校・自治体・企業・医療機関など利用シーンに応じた情報リテラシー・モラルの体系化 |
|
| ・ |
情報の質を創造する、マルチメディア・マークアップ言語・Webサービスなどの情報技術の研究 |
| ・ |
クラウドコンピューティング・SNS・ツイッター・ユビキタスシステムなど、変貌する情報環境における情報の質や新たなサービスの研究 |
| ・ |
情報システムとその環境の質的向上を目指す、データマイニング・機械学習・知能化技術・知能システム科学の研究“高信頼情報社会”の実現を目指す |
|
| ・ |
高信頼情報の特性を自治体・企業・医療機関などで100%活用し、社会に新しい価値を提供するための情報システムの開発 |
| ・ |
情報セキュリティとクォリティ・オブ・ライフの適切なバランスを実現するシステム環境の研究 |
| ・ |
情報とシステムへの信頼を支える社会科学的メカニズムと社会技術の創出 |
|
| 本コースは、米国カーネギーメロン大学と連携し、兵庫県立大学とカーネギーメロン大学の2つの学位(修士)が2年間で取得できる「ダブルディグリー・プログラム」を開設しています。 |
| “高信頼情報”は“安全・安心かつ質の高い情報”として定義されます。クラウドコンピューティングなどの出現で複雑化する環境において、情報を社会に有効に役立てるには、高信頼情報の活用を促進することが唯一の道です。本コースでは、“安全・安心”の観点と“質”の2つの観点から、情報を取り扱う技術や情報のあり方を研究する一方、“高信頼情報”を社会で有効に役立てるための情報システムについても研究を行います。情報の“安全・安心”は、情報インフラ構築・情報マネジメント・情報利用の3つの局面から構成され、機密性(漏えいしないこと)・完全性(改変されないこと)・可用性(必要な時に使えること)を重要な属性とします。情報インフラを考える時は、暗号理論などの情報セキュリティ技術を、理論と実践の両面から論じる必要があります。情報マネジメントに関しては、ISMSなどの認証制度やISO27001などの国際標準による体系化と、阪神・淡路大震災などで得られた具体事例(ベストプラクティスと課題)の両方を踏まえ、実践的な手法の開発に取り組む必要があります。情報利用に関しては、場面に応じた情報リテラシーの体系化には、未だ問題が山積しています。一方、情報の“質”とは、その情報内容に信頼性があるかという観点からの評価であり、インターネットのような発信過多に陥る傾向のある環境で、社会的メカニズムとしてどのように“質”を保証できるかは未解決の問題です。本コースでは、上に述べたような多面的な視点から“高信頼情報”のあり方を研究すると共に、近年顕在化してきた企業等のニーズに応え、技術とマネジメントの両方の観点から情報の安全・安心と質を考えることのできる、高信頼情報科学技術の専門家の育成を目指します。 |
| 修了者の活躍が期待される場 |
| (1) |
企業・地方自治体における企画、情報システム、情報セキュリティの各部門 |
| (2) |
特に、将来CIO (Chief Information Officer)などとして、組織の情報政策を担当する幹部候補生 |
| (3) |
情報機器製造企業における企画、開発、研究の各部門 |
| (4) |
ソフトウェア開発企業における企画、開発、研究の各部門 |
|
|
 |
カーネギーメロン大学とのダブルディグリー・プログラム
Dual-Degree Program with Carnegie Mellon University |
 |
| カーネギーメロン大学は、コンピュータサイエンス部門で何年にもわたって全米第1位の評価を受けるなど、情報科学の研究に秀でた名門校として知られています。特に、情報セキュリティに関しては、世界で最も権威のある研究機関のひとつであるCERTを運用していることで有名です。また、米国では、日本より一足先に、技術とマネジメントの両方の専門性を兼備した情報セキュリティ専門家の育成の必要性が提唱されていますが、カーネギーメロン大学では米国の他大学に先駆けて社会のニーズに適合するカリキュラムを開発し、これまでに多くの優秀な専門家を産業界に輩出しています。本コースでは、カーネギーメロン大学との提携により、同大学が情報セキュリティ専門家に授与する修士号 MSIT-IS (Master of Science in Information Technology Information Security)と本研究科の修士(応用情報科学)の両方の取得が可能なダブルディグリー・プログラムを提供します。本プログラムでは、2年間のうち、1年間は神戸において本研究科の用意したカリキュラムに従って学習し、残りの1年間は、米国ピッツバーグにあるカーネギーメロン大学本校キャンパスにおいて、同大学のカリキュラムによる授業を受けることになります。講義は全て英語で行われます。当プログラムにより、世界水準の専門性を備え、かつ、日本固有の事情にも通じた、即戦力となる情報セキュリティの専門家の育成を目指します。 |
| 修了者の活躍が期待される場 |
| (1) |
企業・地方自治体における企画、情報システム、情報セキュリティの各部門 |
| (2) |
特に、将来CIO (Chief Information Officer)などとして、組織の情報政策を担当する幹部候補生 |
| (3) |
情報機器製造企業における企画、開発、研究の各部門 |
| (4) |
ソフトウェア開発企業における企画、開発、研究の各部門 |
| (5) |
外資系企業における企画、情報システム、情報セキュリティの各部門 |
|
|
|
|
 |
 |
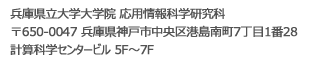 |
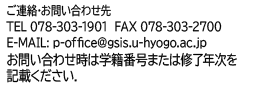 |
|
 |